この記事では、家を建てる費用がどのくらいなのか、さらに頭金や住宅ローンの目安を完全解説します。
家を建てる費用は、住宅金融支援機構の調査によって以下のように明らかにされています。
| 土地ありで家を建てる費用 | 3572万円 |
|---|---|
| 土地なしで家を建てる費用 | 4455万円 |
一方で、家を建てる時に必要になる費用の種類など詳しく理解していない人が多いことも事実。
したがって「土地ありの場合にかかる家を建てる費用」や「土地なしの場合にかかる家を建てる費用」も同時に明らかにしていきます。
あなたに合ったマイホームのプランが気になる方は以下のサービスがおすすめです。
- 土地ありで家を建てる費用は約3,600万円で土地なしだと約4,500万円
- 家をを建てるのにかかる主な費用は土地・建築・その他諸費用の3つ
- 家を建てる際にかかるかかる頭金は住宅価格の1割から2割が目安
- 一軒家を建てるには年収400万円以上が好ましい
- 住宅ローン利用時はオーバーローン・金利の変動・諸費用、利息に注意すべき
- 家を建てる費用によって完成イメージは大きく異る
家を建てる前に売却を考えている方はこちら⇩
【2024年最新】不動産一括査定サイトおすすめ20選の人気比較!選び方や注意点など徹底解説
家を建てる際の費用の全国平均は約3600万円!

住宅金融支援機構が行った調査(2021年度)の調査によると、家を建てる際にかかる費用の目安は全国平均で約3,600万円であることが明らかにされました。
ただ注文住宅と土地付き注文住宅でも価格差があります。
さらに地域によっても大きな差があることは事実です。
ここでは、家を建てる際の費用の平均を明らかにします。
注文住宅の場合は3572万円が平均
建売住宅や注文住宅の所要資金は2021年度 フラット35利用者調査により、以下のように明らかにされています。
| 物件の種類 | 平均価格 |
|---|---|
| マンション | 4,528万円 |
| 土地付き注文住宅 | 4,455万円 |
| 建売住宅 | 3,605万円 |
| 注文住宅 | 3,572万円 |
| 中古マンション | 3,026万円 |
| 中古戸建て | 2,614万円 |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
土地付注文住宅の場合は4455万円が平均
前述の2021年度 フラット35利用者調査より、土地付き注文住宅の平均価格は4,455万円であることが分かりました。
ただ上記した調査結果は全国平均であり、地域によって大きな違いがあることも事実。
そもそも地域によって地価に大きな違いもあり、首都圏と地方では大きな価格差が生まれています。
以下、地域による価格差も明らかにします。
家を建てる費用は地域によっても差がある
| 地域 | 注文住宅の平均コスト |
|---|---|
| 首都圏 | 3,899万円 |
| 近畿圏 | 3,778万円 |
| 東海圏 | 3,650万円 |
| その他の地域 | 3,572万円 |
| 全国平均 | 3,372万円 |
| 地域 | 土地付き注文住宅の平均コスト |
|---|---|
| 首都圏 | 5,133万円 |
| 近畿圏 | 4,658万円 |
| 東海圏 | 4,379万円 |
| その他の地域 | 3,980万円 |
| 全国平均 | 4,455万円 |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
当然ながら首都圏が最も高く、近畿圏さらには東海圏と続きます。
首都圏と近畿圏だけでも平均額には、注文住宅で約100万円、土地付き注文住宅では約500万円もの差があります。
特に土地付き注文住宅の平均コストは地域によって大きな差があり、土地の価格が大きな影響を与えていることは間違いありません。
したがってあなたがどの地域に注文住宅を建てるか、土地付きにするかでも用意しなければならない資金は大きく変わってくるのです。
建売住宅を購入するなら注文住宅がおすすめ!
建売住宅と注文住宅だと、建売住宅の方が安い、といった印象がこれまではありました。
しかし建売住宅が安かったのは過去の話であり、住宅金融支援機構が行った調査(2021年度)によって注文住宅のほうが安いことが明らかにされました。
つまりこだわりを持って造れる注文住宅の方がコストがかからないのですから、建売住宅を購入するのはもったいない話です。
注文住宅のほうがいらない設備などをカットできるため、よりお得な家造りも可能です。
注文住宅にするか建売住宅にするかは、悩ましい問題です。
ただコストを重視するのであれば、注文住宅のほうがおすすめであることが公的な調査からも明らかにされています。
一生に一度と言われる高額な買い物が住宅の購入です。
自由度の低い建売住宅を高く購入するより、自由度の高い注文住宅を安く買うほうがお得でしょう。
家を建てるのにかかる主要な3つの費用

一戸建てを建てるにあたって必要になる費用を大まかなものに分類すると、以下の3つになります。
- 土地の費用
- 建築費用
- その他の費用
それぞれの費用について、まずは簡単に解説していきます。
詳しい金額の目安については次以降の項目で明らかにするので、そちらも合わせてチェックしてください。
土地の費用
一戸建てを建てるためには土地が必要不可欠であり、親から贈与されていたり相続していたりしていなければほとんどが新たに取得します。
注文住宅を購入するに当たり建築費と並んで大きな比率を占めることになるため、事前に地価等を調べた上で適切な地域に適切な価格で購入する必要があります。
土地の料金は都心エリアほど高くなり、同じエリアでも駅が近かったり買い物に便利な地域であったりすると地価は高くなります。
都道府県の公示地価を抜粋して紹介します。
| 地域 | 坪単価平均 |
|---|---|
| 東京都 | 373万3,442円 |
| 大阪府 | 103万488円 |
| 沖縄県 | 45万9,244円 |
| 北海道 | 24万4,465円 |
| 福井県 | 16万9,416円 |
| 山形県 | 10万9,786円 |
| 秋田県 | 8万3,315円 |
| 日本全国平均 | 77万7,599円 |
参考:土地代データ
東京都地方では大きな違いがあることが分かってもらえると思います。
ただ上記した金額は住宅地以外も含んでいるため、必ずしもその金額が土地の平均価格ではありません。
まずは、地域によって大きな違いがある、といったことを理解してもらえたら幸いです。
建築の費用
建物の施工にかかる費用です。
建築の費用は土地代とは異なり、地域による差はそれほど大きくありません。
しかし首都圏は高い傾向にあり、地方は安く抑えられている傾向が若干あります。
以下、住宅金融支援機構が公開している「フラット35利用者調査」の2021年度における建築費の平均額を掲載します。
| 地域 | 敷地面積 | 建設費 | 敷地面積1㎡あたりの建築費 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 252.3㎡ | 3,569.7万円 | 14万円 |
| 首都圏 | 174㎡ | 3,896万円 | 22万円 |
| 近畿圏 | 192.8㎡ | 3,775.7万円 | 20万円 |
| 東海圏 | 239㎡ | 3650.4万円 | 15万円 |
| その他の地域 | 309.3㎡ | 3,368.7万円 | 11万円 |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
また建築業者によってかかるコストが大幅に異なることもあるため、事前に建築費用を問い合わせ確認しましょう。
そのほかの費用
土地と建物にかかる費用以外に、諸費用があります。
代表的な諸費用を紹介します。
- 設計料
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 地鎮祭および上棟式にかかる費用
設計料はハウスメーカーによっては建築費に含めているケースもあるので、見積もりがでた際に質問して聞いておくと良いでしょう。
諸費用は、建築費の5%から10%がベースです。
かりに建築費が3,000万円であれば150万円から300万円になるので、小さな金額ではありません。
土地ありの場合にかかる家を建てる費用

住宅金融支援機構の調査によると、総額3,572万円が土地ありの場合にかかる家を建てる費用の平均値です。
土地をすでに保有している場合は、土地の購入代金は不要です。
したがって土地なしで家を建てるよりも家を建てる費用は安く済みます。
土地ありの場合に家を建てる費用には、以下の4つがあります。
- 家本体工事費用
- 付帯工事費用
- 諸費用
- 地盤調査費用・相続費用
一つずつ解説していくので、土地をすでに保有している方は参考にしてください
家本体工事費用
家本体を建築する費用のことを指しています。
ここには家の外、いわゆる庭や照明、そしてライフラインに関する設備費用は含まれません(付帯工事費用に含まれます)。
家本体工事費用は、ハウスメーカーによっても大きく異なりますし、仕様によっても大きく異なります。
ちなみに家造りに関わる費用のうち70%は家本体工事費用とされています。
- 仮設工事費用
- 基礎工事費用
- 木工工事費用
- 内外装工事費用
- エアコン等の設備設置費用
- 設計料
仮設工事には工事に必要な足場の組み立て、仮設電気、水道、トイレの設置が含まれ、基礎工事にはタ基礎は床下全体にコンクリートを打って作る基礎や建物の壁に沿ってコンクリートを打つ工事が含まれます。
木工工事はその名のとおりに木材を主原料とする加工や組み立てであり、その取付けを指します。
内外装工事の外装工事は外壁、屋根、屋上防水や塗装、壁のサイディングなどを指し、素材によってコストは大きく異なります。内装工事は床フローリング・タイル貼り、クロス貼りなどです。
エアコンなど空調工事も家には必須であり、キッチンや浴室の換気扇もこちらに該当します。
設計は注文住宅の肝と言えるもので設計事務所の実績や料金設定で大きく異なるのが特徴であり、建築費用全体のうち10%から15%を占めます。
付帯工事費用
総費用の15%から20%程度が目安とされています。
- 外構工事(駐車場・庭・門・塀)
- ライフライン工事(水道やガス本管を家に引き込む)
- 取付工事(照明やエアコン、カーテンなどの購入費および工事費)
- 解体工事(古い家の解体)
外構工事は駐車場や庭などにかかる費用であり、造園業者など専門業者へ依頼する場合は別途費用として準備する必要があります。
ライフライン工事は水道管、ガス管工事を指しており、水道管の引き込み工事の相場は30万円から50万円で、ガス管は1メートル引き込むのに1万円程度が相場とされています。
取付工事は照明やエアコン、カーテンなどの購入および取り付けを指しており、電気のスイッチやコンセントカバーなどの取り付毛なども含まれます。

解体費用は買った土地に古い家が建っていなければ発生しません。
解体費用の相場は40坪の家で80万円から120万円、50坪の家なら100万円から150万円、60坪の家なら120万円から180万円程度です。
諸費用
建物や建物まわりの建築工事以外にかかる費用であり、建築工事費用全体の5%から7%程度が目安とされています。
- ハウスメーカーや工務店との契約費用
- 不動産取得および住宅ローンの税金
- ローン費用
- 保険料
- 地鎮祭および上棟式
- 家具家電の購入費用
- 引っ越し代金
ハウスメーカーや工務店との契約費用は工事請負契約にかかる手数料や印紙台を指しています。
不動産取得および住宅ローンの税金は多岐にわたり、印紙税や登記にかかる登録免許税、不動産取得税などが該当します。

ローン費用は融資事務手数料や保証料であり、保険料は火災保険・地震保険・団体信用生命保険料のことです。
家を建てるにあたり地鎮祭や上棟式もおこなわれ、神主さんへの謝礼として初穂料は3万円程度でお供物は1万円程度が相場とされています。
上棟式は基礎工事が完了して建物の骨組み完成時におこなわれ、お供え物や大工さんへご祝儀、昼食が必要で、棟梁への祝儀は1万円から2万円程度、大工さんへは1人あたり5千円が目安です。
新しい住まいでは家具家電も必要なので、事前に購入費用をリストアップしましょう。
引越し代も必要であり、前もって業者に見積もりしてもらうのがおすすめです。
地盤調査費用・相続費用
地盤改良工事が必要になることもあるため、地盤調査費用が発生することもあります。
一般的に行われることが多いスウェーデン式サウンディング試験は5万円程度が目安であり、ボーリング調査をすると25万円から30万円程度かかります。
仮に地盤改良工事をすると、費用の目安は50万円から100万円程度です。
土地が相続したものであれば、相続費用が発生します。
諸費用で解説した税金に該当するもので、相続登記の登録免許税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

土地なしの場合にかかる家を建てる費用

住宅金融支援機構の調査によると、総額4,455万円が土地なしの場合にかかる家を建てる費用の平均値です。
土地なしだと土地の購入代金が必要になるため、土地ありよりも費用が高額化します。
土地なしの場合に家を建てる費用には、以下の4つがあります。
- 家本体工事費用
- 付帯工事費用
- 諸費用
- 土地購入費用
一つずつ解説していくので、土地をまだ保有していない状態で住宅の購入を考えている方は必見です。
家本体工事費用
住宅本体にかかる費用であり、家を建てる費用の大部分を占めるものです。
建物の階数によっても家本体工事費用は異なります。
建築費用(坪単価)は同じ床面積でも、平屋建てより2階建てのほうが安くなる傾向があります。
建物の屋根や基礎部分(コンクリート)は家本体工事費用の中でも、特に高額な部分です。
したがって平屋建てだと2階建てより屋根や基礎部分の面積が大きくなるため、費用が膨らんでしまうのです。
付帯工事費用
主に3つの工事が該当します。
| 工事 | 内容 |
|---|---|
| 地盤改良工事費 | 地盤を改良するための工事 |
| 外構工事費 | 庭や門、塀や駐車場などの工事 |
| 屋外給排水工事費 | ガス管および水道管を引き込む工事 |
屋外給排水工事費はハウスメーカーによって取り扱いが異なるので、事前に確認しておく必要があります。

いずれの工事も、内容によっては100万円を超えることもあるため要注意です。
諸費用
主に以下の3つの費用が該当します。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン手数料 | 金融機関に支払う手数料 |
| 保険料 | 火災保険等の保険料 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(※土地購入費用に含まれる) |
土地購入費用
土地購入費用は、広さや地域によっても大きく異なります。
住宅金融支援機構が行った調査(2021年度)で、フラット35の土地付注文住宅融資利用者の土地取得費用が地域別に明らかにされているので掲載します。
| 地域 | 土地取得費 |
|---|---|
| 首都圏 | 2,220.9万円 |
| 近畿圏 | 1,693.1万円 |
| 東海圏 | 1,274.3万円 |
| その他の地域 | 912.3万円 |
| 全国 | 1,444.9万円 |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
その他の地域と首都圏では倍以上の開きがあるため、あなた自身がどこに家を建てようとするかでも土地の購入費用の予算設定は大きく変わってきます。
希望地域の地価を前もって調べておきましょう。
家を建てる際にかかる費用の頭金はいくら?

頭金は、分割払いを行う際に最初に支払うまとまった額のお金です。
近年ではフルローンと呼ばれる住宅費用を全額賄うタイプのローンもありますが、契約時に支払うコストもあるため、ある程度まとまった資金を前もって確保しておく必要があります。
ここでは家を建てる際にかかる費用の頭金はいくらなのか、さらに平均額などについて解説します。
そもそも家を建てるときの頭金とは?
住宅が3,000万円であり、そのうち住宅ローンで賄うのが2,600万円とすると頭金は400万円です。
つまり住宅価格から住宅ローンによる借入額を差し引いた金額が頭金なのです。
頭金を多く用意できれば、それだけ住宅ローンの利用額が少なくなり審査が有利になります。
それだけではなく借入額も少なくなるため、月々の返済額が低くなったり、返済期間が短くなったりするなど返済の負担が軽くなります。
住宅の種類別!頭金の平均額一覧
住宅金融支援機構による「2021年度 フラット35利用者調査」から、消費者がどの程度の頭金を用意して住宅を購入しているかが分かります。
以下、すでに土地を保有している注文住宅購入者の頭金の平均額を地域別に掲載します。
| 地域 | 頭金平均額 | 住宅購入全体費用からみた割合 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 737.5万円 | 18.9% |
| 近畿圏 | 676.6万円 | 17.9% |
| 東海圏 | 581.1万円 | 15.9% |
| その他の地域 | 522.2万円 | 15.5% |
| 全体 | 596.6万円 | 16.7% |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
以下、土地付き注文住宅購入者の頭金の平均額を地域別に掲載します。
| 地域 | 頭金平均額 | 住宅購入全体費用からみた割合 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 508.7万円 | 9.9% |
| 近畿圏 | 429.6万円 | 9.2% |
| 東海圏 | 379.1万円 | 8.6% |
| その他の地域 | 354.6万円 | 8.9% |
| 全体 | 412.3万円 | 9.3% |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
すでに土地を保有している方は、土地の取得費用が必要ないためローンは比較的少額で済みます。
したがって住宅購入全体費用からみた頭金の割合は、土地付き注文住宅購入者のほうが高いです。
家を建てる際に頭金を払うべき?
状況に合わせて考えるべきです。
以前は頭金ゼロで住宅の購入は不可能でしたが、現在では頭金なしでも住宅は購入できます。

以上のように考える方もいますが、頭金なしにはいくつか問題点があります。
- 審査難易度が上がる
- 借入額が増え利息負担が大きくなる
- 諸費用分は現金が必要
重要なテーマなので一つずつ解説します。
審査難易度が上がる
頭金なしだと、より高額の住宅ローンを組むことになります。
金融機関側としては貸し倒れが怖いため、審査難易度を引き上げます。
あなたの勤務先や年収などの条件が良ければ、頭金なしでも住宅ローンが組めるかもしれません。
しかし属性情報などにちょっとした問題でもあると、金融機関側が不安視して審査落ちにしてくる可能性が高まります。
借入額が増え利息負担が大きくなる
頭金は数百万円になるのが一般的であり、頭金なしとなるとその数百万円分も大きなローンを組みます。
借入額が増えるため月々の返済額も高額化し、利息の負担も重くなります。
たしかに住宅ローンの金利は1%台から2%台と低く設定されていますが、借金額自体が高いので、年間で数十万円の金利が発生するのです。

諸費用分は現金が必要
不動産を購入する際は、物件の購入費用以外にも様々な諸費用が発生します(契約費用や税金など)。
それらは住宅ローンに含められないため、一定の資金は自身で用意しなければなりません。
そもそも諸費用の支払いは現金一括払いが基本なので、完全に手持ち資金ゼロで住宅は購入できないので要注意です。
家を建てる費用と年収の関係性
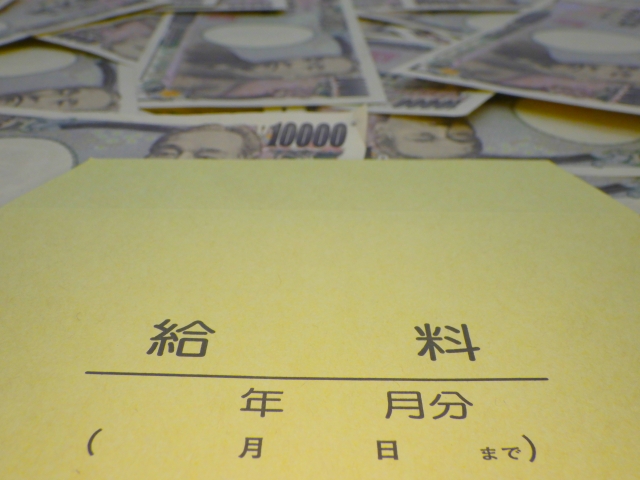


注文住宅を建てるには土地購入費や建築費用がかかります。
特に住宅ローンの審査に大きく関わるのが年収であり、当然低年収であれば審査落ちの原因になることも…。
ここでは家を建てるコストと年収の関係性に徹底的に迫ります。
信頼できるデータ(住宅金融支援機構)を元に必要な年収額を算出していくので、自身の収入を当てはめてみてください。
一軒家を建てるなら年収400万円〜
住宅金融支援機構の「2021年度 フラット35利用者調査」によると、年収400万円以上600万円未満の世帯が中心になって家を建てていることがわかります。
以下、調査結果を掲載します。
| 年収 | フラット35利用者割合 |
|---|---|
| 400万円未満 | 22.2% |
| 400万円以上600万円未満 | 40.1% |
| 600万円以上800万円未満 | 20.3% |
| 800万円以上1,000万円未満 | 8.9% |
| 1,000万円以上1,200万円未満 | 3.6% |
| 1,200万円以上 | 4.9% |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
フラット35利用者全体の平均年収額は608万円であることも明らかにされています。
一方で400万円未満でも家を建てている人がおり、比較的低いとされる収入でも住宅を得ている人がいることが分かります。
したがって一軒家を建てるなら年収400万円以上あれば、収入としては大きな問題はありません。
ただ400万円前後だと、今後収入の上昇が見込める、たとえば20代や30歳前後といった若い人でなければ難しいでしょう。
住宅ローンは年収の何倍まで?
こちらもフラット35の調査結果により明らかにされており、2021年の平均は6.8倍でした。

またフラット35の公式ページに、ローンシミュレーションのコーナーが設けられています。
そちらでは年収と金利を入力すると、概算の借入可能額を算出してくれます。

ただ、画像のとおりに500万円の年収で約9倍に当たり4,548万円の借入可能額が表示されるなど、金額が高くなりがちです。
ローンシュミレーションの数字は、参考程度にとどめておきましょう。
一ヶ月あたりの返済額は世帯収入の20%
住宅ローンを利用したら、毎月の返済をしなければなりません。
そこで注目したいのが、収入あたりの返済額の割合です。
適切な返済額を設定しなければ、返済に困り対応することも考えられます。
滞納したら、家を競売にかけられ失う恐れも…。
月あたりの返済負担率も住宅金融支援機構の「2021年度 フラット35利用者調査」によって明らかにされています。
| 月収あたりの返済負担率 | フラット35利用者割合 |
|---|---|
| 10%未満 | 4.5% |
| 10%以上15%未満 | 10.9% |
| 15%以上20%未満 | 19.2% |
| 20%以上25%未満 | 23.3% |
| 25%以上30%未満 | 28.2% |
| 30%以上 | 13.9% |
参考:住宅金融支援機構 2021年度 フラット35利用者調査
平均返済負担率は22.7%です。
つまり月収35万円の方であれば、その22.7%の約8万円が毎月の返済額の目安に。
返済負担率を上げれば早く返済が終わるため、利息の支払いも抑えられます。
しかし月々の負担が重くなるので、調査結果も参考に返済負担率はなるべく20%を目安にしましょう。
家を建てる費用のローンに関する3つの注意点

住宅ローンを利用するにあたり、前もって把握しておきたい注意点が3つあります。
- オーバーローン
- 金利の変動
- 諸費用・利息の額
住宅ローンを利用するにしても、リスクがあることは理解しておかなければなりません。
家を差し押さえられるような状況にしないためにも、注意点を理解し、そのうえで対策を立てましょう。
オーバーローンに注意する
オーバーローンとは、物件価格以上の融資を受けることです。
つまり物件の購入価格は4,000万円なのに、4,500万円を借りるようなケースがオーバーローンに該当することに。
そもそも住宅を購入する際は諸費用(印紙税や登録免許税、不動産取得税など)がかかり、一般的な住宅ローンは諸費用をカバーしていません。
つまり自腹で支払わなければならないため負担に感じ、オーバーローンを利用して諸費用も賄おうと考える人も多いです。
しかしオーバーローンは、より多くの資金を借り入れることになり返済の負担が重くなります。
月々の返済額も高額になるため、諸費用に関しては自前で用意できる状況にしましょう。
物件価格+諸費用以上にお金を借りる行為で、新居用の家具や車などをそのローンで買ってしまおうとするものです。
ただ住宅ローンは住宅関連費用のローンであり、その他の目的で利用するのは規約違反です。
強制的に契約解除され一括返済を求められても文句は言えません。
詐欺罪や私文書偽造罪、偽造私文書行使罪などの違法行為に該当する恐れもあるため、絶対におこなわないでください。
金利の変動に注意する
現在、日銀の金融緩和策が続いており低金利が続いています。
住宅ローンにとっては有利な状況ですが、今後はどのように変化するか分かりません。
一気に金利が跳ね上がる可能性もあるため、変動金利で住宅ローンを利用すると想定以上の利息を支払う恐れもあるのです。
したがって、住宅ローンの金利は基本的に「固定金利」を選びましょう。
かりに固定金利でさらに金利が下がった場合は、「借り換え」で対処すればOKです。
諸費用・利息の額に注意する
住宅ローンを組むためには、様々な費用が発生します。
以下に住宅ローンの代表的な諸費用と費用の目安を明らかにします。
| 費用 | コストの目安 |
|---|---|
| 融資手数料 | 3万円から5万円程度 |
| 斡旋手数料 | 数万円から数十万円程度 |
| ローン保証料 | 融資額1,000万円あたり20万円程度 |
| 地震保険証 | 保証額1,000万円あたり1万円から3万円 |
| 火災保険料 | 15万円から40万円程度 |
| 団体信用生命保険料 | 10万円から12万円程度 |
ローンによっては金利に上乗せされているケースもあるため、ローンを組む際は必ず確かめてください。
家を建てる費用別にわかる注文住宅のイメージ

家づくりの予算は、どんな家を建てたかによっても大きく異なります。
まずは自分がどのような住宅を望んでいるかを明確にして、そのうえでどの理想の実現にはどの程度のコストがかかるのかを知ることが大事です。
ここでは、1,000万円台から5,000万円台のコストで建てられる家の特徴を明らかにします(土地代は含みません)。
それでは、それぞれどんな家が建てられるのでしょうか?
家を建てる費用が1000万円台の場合
比較的若い世帯であると、住宅ローンが年収によって大きく制限を受けることもあるでしょう。
頭金を用意するのが難しいケースも珍しくありません。
建築費用が1,000万円台であると出来ることはかなり限られるため、様々な項目の取捨選択に迫られます。
一般的には建物の形状はシンプルで片流れ屋根が適しており、間仕切りを少なくしたうえで設備や内装・外装の素材のグレードを抑えられれば1,000万円台でも家造りは十分に可能です。
以下、1,000万円台の家造りの特徴をまとめます。
| 坪数 | 20坪後半から30坪前半が対象 |
|---|---|
| 建物の形状 | シンプルな作り(凹凸が少ない) |
| 設備と素材 | 低グレードが中心 |
| 内装 | 壁面積を減らす(室内の間仕切りを少なくする) |
| 外構と植栽 | 必要な部分のみ(住み始めてから順次対応) |
家を建てる費用が2000万円台の場合
2,000万円台の用意ができる状態であれば、1,000万円台よりもこだわった家造りが可能です。
特に坪数やグレードに余裕が生まれるので、個性のある家を求めている方は最低でも2,000万円台の建築費用は準備しましょう。
ただ2,000万円台でも予算が豊富とはいえないので、メリハリを付けることが肝心です。
特に建物の形状はコストがかかるので、ここにコストを掛けると設備や素材や内装などにお金がかけられなくなります。
したがって、外観はなるべくシンプルなものにしましょう。
延床面積についても30坪代後半が見えてきますが、あまりに広くすると他の部分にコストが割けなくなるため、なるべく抑制することをおすすめします。
以下、2,000万円台の家造りの特徴をまとめます。
| 坪数 | 建物や外構にコストを掛ける場合は坪数を抑える |
|---|---|
| 建物の形状 | シンプルな作り(凹凸が少ない) |
| 設備と素材 | こだわりたい部分とそうでないところを分ける |
| 内装 | 間仕切りは極力減らす |
| 外構と植栽 | 必要な部分のみ(住み始めてから順次対応) |
家を建てる費用が3000万円台の場合
全国の平均予算に近いので、一般的な家造りをしたい方にとって最適な予算となります。
間取りおよび外観など様々な希望が取り入れやすくなり、広めのリビングにオーディオ設備などを設置することも可能です。
他にもキッチンや浴室にも拘れるようになるため、家そのものをグレードアップさせられます。
坪数もある程度までは対応できるようになり、多少広めの家を希望している方にもおすすめの予算額です。
以下、3,000万円台の家造りの特徴をまとめます。
| 坪数 | 30坪後半から40坪前後まで対応可能(地域によってはそれ以上も可) |
|---|---|
| 建物の形状 | 凹凸ある個性的なデザイン可 |
| 設備と素材 | グレードの高い設備&素材を選択可能 |
| 内装 | 天井に勾配をつけたり、1階と2階の両方にシャワールームを作ったりすることも可能 |
| 外構と植栽 | 家の建築と同時に完成可 |
家を建てる費用が4000万円台の場合
予算的にも余裕が出てくるため、自由度の高い家が建てられます。
延床面積は40坪以上も狙え、建物の形状もL字型やコの字型など特徴的なものを選べます。
- 天然木の床素材
- しっくい壁
- 床暖房
- 全面タイルの外観
以上のようなものも導入できるため、こだわりのある家造りを検討している方は4,000万円台の予算の用意をおすすめします。
以下、4,000万円台の家造りの特徴をまとめます。
| 坪数 | 二世帯住宅も可能 |
|---|---|
| 建物の形状 | 凝ったデザインも可能 |
| 設備と素材 | 高品質な素材を選択可能 |
| 内装 | 輸入物や伝統工芸品も導入可能 |
| 外構と植栽 | デザイン残った庭が作成できる |
家を建てる費用が5000万円以上の場合
建築費用の予算が5,000万円以上であれば、全国平均の1.5倍以上です。
家の広さはもちろんですが、室内外の設備および装備、さらには外構にかけられる予算も多くなるので建売住宅とは一線を画すこだわりの家が実現できます。
- ゲストルーム
- 防音設備の整った地下室
- エレベーター
以上のような特別室のようなものを設けられる可能性もあります。
以下、5,000万円台の家造りの特徴をまとめます。
| 坪数 | 40坪後半以上も狙える |
| 建物の形状 | デザイナーハウスのような凝った外観もOK |
| 設備と素材 | 高額な輸入材の利用も可能 |
| 内装 | ドアに1枚ものの木材、床材に天然木の総ひのきが選べることも |
| 外構と植栽 | デザイン性の高い庭が作成できる |
家を建てる費用まとめ
家を建てる費用を徹底解説しました。
- 家を建てるには建築費用だけで平均3,600万円が必要
- 頭金が不要の住宅ローンもあるが状況に合わせて判断すべき
- 住宅ローンは年収の約7倍まで対応可能
- 住宅ローンの返済額は月収の20%程度がおすすめ
- 1,000万円台から家は建てられるがこだわりの強い家は3,000万円台から
家を建てるのにかかるコストは、建築費用だけで全国平均で約3,600万円です。
高額であるため、ほとんどの方が住宅ローンを利用するでしょう。
そのため住宅ローンについても詳しく解説し、ローン利用額は年収の約7倍程度で月の返済額は20%前後が平均であることも明らかにしました。
無理な返済計画は、のちの生活に大きな影響を与えかねません。
新しい家に住み始めてからの生活も意識し、そのうえで予算を組むのがおすすめです。
準備できる資金や組めるローン額は人それぞれなので、無理のない返済計画で安心の家づくりを目指しましょう。
また、家をお得に建てるなら複数のハウスメーカーを比較検討することが重要です。
複数のハウスメーカーを比較することで、予算を低く抑えながら、あなたの作りたい理想のマイホームを設計してもらうことができます。



