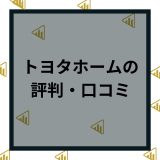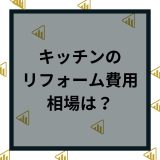注文住宅を建てるにあたって決めることも多く、何から手をつけたらいいのかわからないという人も少なくありません。
そこで本記事では、家づくりの流れやかかる費用の相場、予算の組み方について解説していきます。
初めて家づくりを検討している人はぜひ参考にしてみてください。
家づくりの流れと入居までのスケジュール

家づくりの計画を立てるには、まず大まかな流れを知っておく必要があります。
流れを理解することで、スタート時期を逆算することができます。
ここでは、注文住宅が完成して入居となるまでの流れと目安の期間について、解説していきます。
家づくりの流れ
家づくりを始めてから入居となるまでは、基本的に以下のような流れで進行します。
家づくりの流れの中には、準備期間やプランニングのような時間が読みづらい工程もあります。
そのため、期間が大幅に変わってしまうことも少なくありません。
トータルでかかる期間を考えると、早ければ半年、長ければ1年以上かかるケースもあります。
スタートのタイミングは慎重に検討する必要があります。
家づくりの目安期間
家づくりを始めてから入居にかかる目安期間は、一般的に以下のようになります。
実際に家づくりをするとなると、期間通りに進むわけではありません。
一つの目安として、これだけの期間がかかることを覚えておきましょう。
慎重にスケジュールを立て、無理に早く済ませようとしないとしないのもポイントです。
工事の具体的な内容
着工後には、基本的に施工会社に委託することになり、工事は以下のように進行していきます。
- 地盤調査
- 基礎工事
- 上棟
- 屋根工事
- 外壁工事
- 断熱、設備工事
- 完成工事、外構工事
偏に家づくりと言っても、さまざまな工事を経て、家は完成していきます。
実際にどんな工事が必要までかは理解しておく必要はありませんが、施工会社と話し合いをする際に強く出ることができます。
注文住宅でかかる費用とは?

家づくりの大まかな流れを把握できたら、次に注文住宅でかかる費用についてみていきましょう。
ここでは、注文住宅の購入資金の平均や土地にかかる費用、諸費用としてかかるお金について、詳しく解説していきます。
あなたの建てたい家にはどれだけお金が必要なのか、これをみて参考にしてみてください。
注文住宅の購入資金平均額
住宅金融支援機構によると、土地付き注文住宅の平均所要資金は、以下のようになっています。
- 首都圏:5,160万円
- 近畿圏:4,542万円
- 東海圏:4,410万円
- 全国平均:4,390万円
土地の価格には地域差が大きく影響しますが、購入を検討しているエリアの平均価格を確認しておきましょう。
逆に既に所有している土地に家を建てたい場合には、注文住宅のみの費用になるので、上記の価格よりも安くなります。
目安として、既に土地を所有している場合の全国平均所要資金は「3,530万円」となっています。
既に土地を購入している場合や相続した土地がある場合には、建築に必要な費用を中心に予算を検討するようにしましょう。
土地にかかるお金
家を建てるには土地が必要になります。
親からの贈与や相続、既に自分で購入していた場合を除けば、多くが新しく土地を購入することになるでしょう。
注文住宅を購入するのにおいて、「建築費用」のように大きい比率を占めるのが「土地代」です。
「土地代」はエリアごとによって非常に大きな差が出るもので、都心エリアに近づけば近づくほど高くなってしまいます。
また、同じエリアであっても、交通の便や買い物がしやすい立地などによっても土地価格は反映されます。
以下では、エリアごとの平均の地価をまとめてみました。
| エリア | 1㎡あたりの平均地価 |
|---|---|
| 東京圏 | 約25万円 |
| 大阪圏 | 約17万円 |
| 名古屋圏 | 約14万円 |
| 地方(人口10万人以上) | 約5万円 |
エリアごとの平均の地価をみると、東京圏と地方では5倍近い差があることがわかります。
また、同じ東京圏であっても人気で交通の便がいい場所だと平均地価は数倍に高くなります。
場所にこだわりがない場合には、郊外に家を建てることで、建築費に土地代の差額を当てることができるのでおすすめです。
多少都心から離れた場所に土地を探すことで、地価を抑えた家づくりをすることが可能になります。
また、建物にこだわりがなく交通の便を重要視したい場合には、建売住宅を検討するのが安く費用を抑えることができます。
建物にかかるお金
土地の所有について理解した後に、建物の施工について解説していきます。
注文住宅は建売と比較して建物に必要な費用が大きくなっているので、相場の価格はしっかりと把握しておく必要があります。
以下に、建築費用と1㎡あたりの建築費をまとめてみました。
| エリア | 床面積 | 建築費用 | 1㎡あたりの建築費 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 126㎡ | 3,390万円 | 約27万円 |
| 首都圏 | 125㎡ | 3,690万円 | 約30万円 |
| 近畿圏 | 127㎡ | 3,500万円 | 約27万円 |
| 東海圏 | 128㎡ | 3,450万円 | 約27万円 |
| その他地域 | 127㎡ | 3,230万円 | 約25万円 |
注文住宅の建築費用はエリアによって、大差はないようにですが、首都圏はやや高い傾向にあります。
土地付きの注文住宅の場合には、ハウスメーカーや工務店が指定されます。
そのため、数百万円ほどの価格差が出てくるため、事前に建築費用については問い合わせておきましょう。
諸費用としてかかるお金
![]()
上記のように感じる人も少なくないでしょう。
家づくりには土地代と建築費用の他に、諸費用がかかってしまいます。
注文住宅を建てる際に必要になる諸費用は主に以下のようなものがあります。
| 項目 | 費用の相場 |
|---|---|
| 設計料 | 建築工事費の10%程度 |
| 仲介手数料 | (物件価格 × 3% + 6万円) |
| 印紙代 | 物件が1,000万円〜5,000万円以下の場合、1万円 |
| 登録免許税 | 土地価格の1.5% |
| 司法書士の報酬 | 20万円〜25万円程度 |
| 地鎮祭、上棟式 | 5万円〜10万円程度 |
上記以外にも上下水道やガス管の引き込み工事や水道加入金などのかかってくる費用があります。
諸費用の目安として、「建築費用の5%〜10%程度」と考えておきましょう。
実際には引越し費用などもかかるため、余裕のある予算計画を立てておきましょう。
注文住宅の予算を組むには?

家づくりの流れで紹介したように、注文住宅の予算を組むのは一連の流れで重要なポイントです。
ここでは、予算を組む流れや頭金のメリットや目安、注意点について詳しく解説していきます。
予算を組む流れを十分理解して、しっかりと計画的に行えるようにしましょう。
予算を組む流れ
家作るの予算を決める際の重要なポイントは、「どれだけの頭金を用意できるか」ということです。
次に年収やライフプランなどの情報から住宅ローンで借りる必要のある金額を検討しましょう。
家づくりの予算としては、住宅ローンの借入金額と頭金の合計金額を考えるようにしましょう。
頭金のメリットと目安
頭金とは、住宅購入資金の中で自分たちで用意できるお金のことを言います。
頭金の割合は特に指定されておらず、任意で割合を決定することができます。
注文住宅を建てるタイミングや計画によっては、全く頭金を用意できずにフルローンで住宅を購入する人も少なくありません。
しかし、住宅ローンの借入金額が大きければ大きいほど、利息分も大きくなってしまいます。
そのため、頭金を用意してから注文住宅を検討した方が必要な金額を抑えられるため、おすすめです。
住宅ローンの中には、一定以上の頭金を用意することで利率を下げられるものもあります。
目安として、注文住宅に必要な価格の10%〜20%程度の頭金を用意するようにしましょう。
頭金の注意点
先ほどの説明を見ていると、頭金は出せるだけ出したほうがいいと考えている人もいるでしょう。
しかし、頭金を準備する際には「諸費用や生活費として必要な一定の現金を残しておく」必要があります。
注文住宅の諸費用の多くの項目で現金での支払いが求められるため、資金がない状態で手続きをすることはできません。
引越し代や家具の購入代など、想定される出費を支払うためにも、ある程度の余力は残しておきましょう。
住宅ローンの仕組みと借入金額の決め方

頭金が決定したら、住宅ローンの借入金額を検討するようにしましょう。
ここでは、住宅ローンの借入金額に強く影響する項目と、具体的な金額を決める方法を解説していきます。
実際に住宅ローンの借入金額を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン金利とは?
住宅ローンには、主に以下の3種類の金利タイプがあります。
- 固定金利型
- 変動金利型
- 固定金利期間選択型
上記の金利タイプの住宅ローンからどの金利タイプを選択するかによって、返済額に大きな違いが生まれます。
そのため、それぞれの金利タイプの特徴を押さえた上で利用するようにしましょう。
固定金利型
固定金利型とは、契約から完済するまで金利が変動しないタイプのことを言います。
当初おn金利は他のタイプよりも高めに設定れていますが、完済するまで金利が変動しないため、安定した返済計画を考えることができます。
金利変動のリスクがなく、返済計画が立てやすいことは非常にメリットになります。
変動金利型
変動金利型とは、経済状況の変化に合わせて、半年ごとに金利調整が行われるタイプのことを言います。
変動金利の場合には、金利が変動してしまうリスクはありますが、当初の金利は低絵に設定されています。
さらに、返済額の上昇幅についても前回の返済額の1.25倍までと規制されているので、極端に返済額が変化することはありません。
返済期間を短くすることができ、すぐに完済を目指したい方におすすめの金利タイプと言えます。
固定金利期間選択型
固定金利期間選択型とは、スタートから一定期間の金利が固定されており、その期間が終了すると再度金利タイプを設定するタイプのことを言います。
住宅ローンの借入から5年などの一定期間が経過したタイミングで、あらためて金利タイプを見直すことができます。
この金利タイプのメリットとして、固定金利と変動金利のメリットの両面を併せ持つということが挙げられます。
しかしながら、変動金利の場合には返済額の上昇幅は1.25倍までの制限があると解説しましたが、固定金利期間選択型には、この制限がありません。
そのため、返済額が急に増えてしまう可能性があるということを十分理解した上で検討するようにしましょう。
返済方法の基礎知識
住宅ローンの返済方法には、以下の2種類があります。
- 元利均等返済
- 元金均等返済
元利均等返済とは、毎月支払う返済額が一定となる返済方法です。
元金均等返済とは、毎月支払う返済額のうち、元金の額が一定となる返済方法です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 元利均等返済 | 返済額(元金+利息)が一定のため、返済計画が立てやすくなります。 元金均等返済に比べて、返済開始当初の返済額を少なくすることができます。 |
同じ借入期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなります。 借入金残高の減り方が遅くなります。 |
| 元金均等返済 | 返済額(元金+利息)は返済が進むにつれ少なくなっていきます。 元利均等返済に比べて、元金の減少が早いため、同じ借入期間の場合、元利均等返済よりも総返済額は少なくなります。 |
返済開始当初の返済額が最も高いため、当初の返済負担が重く、借入時に必要な収入も高くなります。 |
どちらの返済方法が適しているか、しっかりと吟味しましょう。
借入額の決め方
住宅ローンの借入金額を決定する際には、毎月の返済額がいくらになるのか明確にしておきましょう。
毎月の返済額は、現在の家賃の価格を参考に決めることもありますが、持ち家の場合には固定資産税や維持費が加算されるので、多少余裕のある返済額にする必要があります。
毎月の返済額が負担にならないかを判断するために、「返済負担率」という指標をよく用います。
返済負担率とは、年収に対する返済額の総額の割合を示しています。
生活に支障をきたさないラインとして、25%以内が目安になっています。
このようにして、毎月の返済額を設定し、返済期間を考慮することで住宅ローンシミュレーターなどで借入可能金額を計算することができます。
「家を建てたい」ときに決めるべき3つのこと

家づくりにおいて、決めなければいけないことが多く、何かと詰まってしまうことも少なくありません。
ここでは、家づくりを始める前に、事前に決めておくべきことを紹介していきます。
項目別に解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
資金関連で決めること
資金について、事前に決めておいた方が良いのは以下の項目です。
- 頭金の額を決める
- 住宅ローン借入額を決める
- 金利や返済方法を比較検討しながら適したものを選ぶ
- 注文住宅の費用の仕組みと内訳を理解する
- 購入後の生活費と固定費も見込んで無理のない計画を立てる
資金関連はきちんと計画的に考える必要があるので、時間をしっかりかけて決めるようにしましょう。
実際に上記の項目を既に決めていた方が、家の完成までも早くスムーズに家づくりが進んでるケースが多くあります。
土地探し関連で決めること
土地探しでは、大まかに「立地」と「土地の状態」の2つを検討するのが重要になります。
事前に以下の点を決めておきましょう。
- 生活イメージを明確にして住みたいエリアを決める
- 土地購入に充てられる予算を明確にする
- 建てたい家を建築可能かどうか確かめる
- 地盤の状態を確かめる
交通や生活の利便性の他にも、教育環境や病院の有無、周辺の治安などさまざまなことを考慮する必要があります。
立地については、家族の価値観を合わせ、お互いがここがいいというところを見つけ出すまでやることが重要です。
また、土地の状態について、土地によっては建てたい家を建てられない土地も存在します。
例えば、「3階建ての家が建てられない」「建物の広さや屋根の形に制限がある」といった法令上の制限がある土地もあります。
そのため、自分たちで建てたい家のイメージがある程度固まってから、土地探しを行うのがおすすめです。
土地選びには専門的な視点も必要なので、施工会社の方と相談しながら決定するのがおすすめです。
家づくりや間取りで決めること
家づくりや間取りでは、具体的なイメージを掴むことが重要になります。
多くの方が、住宅カタログやモデルハウスなどの事例を通して、理想のマイホームのイメージを掴みますが、より効率的な方法があります。
効率的に理想のマイホームのイメージを掴む方法は以下の通りです。
- 大きなゾーニングから考える
- 部屋の位置を細かくレイアウトする
- 収納スペースの数や広さ、配置を考える
- 窓やドアの位置、大きさを考える
- 住宅性能の種類と特徴を押さえて、重視したいものを明確にする
- こだわりのデザインがある場合は理想に近い事例を探してみる
間取りを決めると言っても細かい部分から決めていくと、調整を行うごとに白紙に近い状態に戻ってしまう可能性があります。
そのため、大きなゾーニングから検討していくことで、後に細かい部分を調整した方が効率的なケースが多いです。
また、断熱性や耐震性のような家の性能面も、住み心地を大きく左右するポイントなので、しっかりと吟味する必要があります。
間取りは後々変えることのできないものなので、自分たちが納得がいくまで考えるようにしましょう。
家づくりの費用やスケジュール、予算の組み方まとめ
いかがでしたか。
今回は家を建てたい人向けに、家づくりの流れやかかる費用の相場、予算の組み方について解説してきました。
家づくりは一生に一度の重要なイベントのひとつです。
後悔しない家づくりにするためにも、しっかりと本記事の内容を理解してください。
もう一度、本記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 首都圏:5,162万円
- 近畿圏:4,540万円
- 東海圏:4,412万円
- 全国平均:4,397万円
- 固定金利型
- 変動金利型
- 固定金利期間選択型
- 元利均等返済
- 元金均等返済
- 頭金の額を決める
- 住宅ローン借入額を決める
- 金利や返済方法を比較検討しながら適したものを選ぶ
- 注文住宅の費用の仕組みと内訳を理解する
- 購入後の生活費と固定費も見込んで無理のない計画を立てる
- 生活イメージを明確にして住みたいエリアを決める
- 土地購入に充てられる予算を明確にする
- 建てたい家を建築可能かどうか確かめる
- 地盤の状態を確かめる
- 大きなゾーニングから考える
- 部屋の位置を細かくレイアウトする
- 収納スペースの数や広さ、配置を考える
- 窓やドアの位置、大きさを考える
- 住宅性能の種類と特徴を押さえて、重視したいものを明確にする
- こだわりのデザインがある場合は理想に近い事例を探してみる
家をお得に建てるなら複数のハウスメーカーを比較検討することが重要です。
複数のハウスメーカーを比較することで、予算を低く抑えながら、あなたの作りたい理想のマイホームを設計してもらうことができます。
複数のハウスメーカーを無料で比較検討するならHOME4Uがおすすめです。
HOME4Uでは、大手ハウスメーカーから無料で見積もりをもらうことができ、提案や交渉で有利になります。
まずは一度HOME4Uで比較検討してみましょう。